インフルエンザワクチンはいつ打てばいい?効果は何時間後から?持続時間は?について医師が解説
- 2025年10月14日
- インフルエンザについて
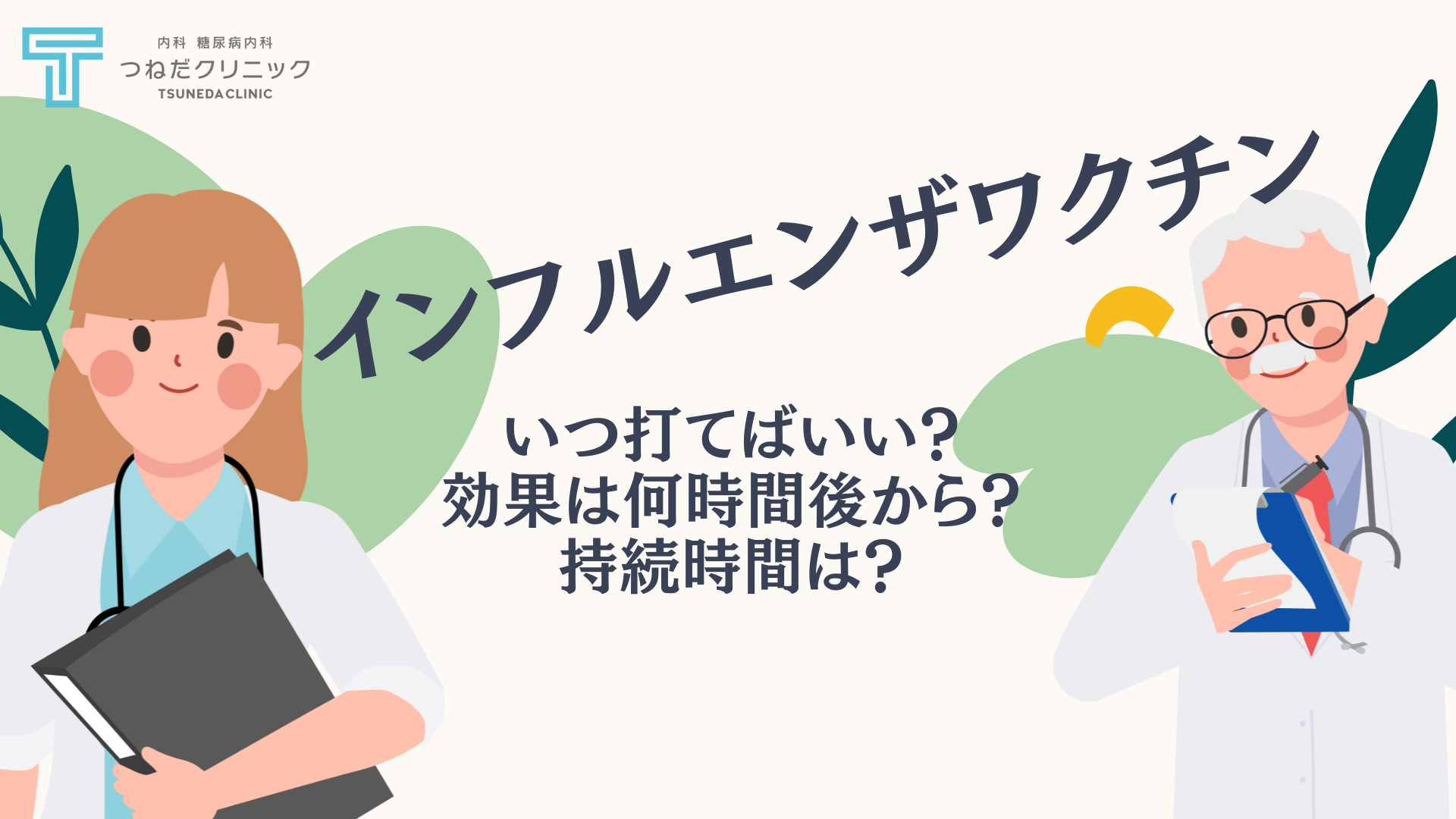
インフルエンザが流行する季節が近づいてきました。ワクチンは“冬の備え”です。「インフルエンザワクチンはいつ打てばいいの?」「効果はワクチン接種後いつ頃から出るの?」「どれくらい持続するの?」──このような疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、糖尿病内科を専門とする医師の立場から、最新のエビデンスに基づいてわかりやすく解説します。
インフルエンザワクチンとは?効果や目的をわかりやすく解説
インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルス(A型・B型など)の感染を防ぐために作られた不活化ワクチンです。主成分はウイルスの表面たんぱく質「ヘマグルチニン(HA)」で、これを体内に少量入れることで免疫システムが「抗体」を作り、実際の感染時にウイルスをすぐに攻撃できるようになります。
目的は「発症を防ぐ」ことだけでなく、「重症化を防ぐ」ことにあります。特に糖尿病・心疾患・高齢者などの方では重症化しやすいため、接種によるメリットが大きいです。使用される代表的な製剤は「フルービックHA(一般名:インフルエンザHAワクチン)」などで、国内では毎年ウイルス株が更新されます。ここではまず、インフルエンザの感染経路とワクチンの基本的な仕組みをお伝えします。
インフルエンザの感染経路と流行時期
インフルエンザは主に「飛沫感染」と「接触感染」で広がります。咳やくしゃみの飛沫を吸い込んだり、手すりなどに付着したウイルスに触れて感染します。日本では例年12月〜3月が流行のピーク。ワクチン効果が出るまで時間がかかるため、11月上旬までの接種がおすすめです。(参考:国立感染症研究所「インフルエンザとは」)
インフルエンザワクチンの仕組みと免疫の働き
ワクチンには「不活化ウイルス(感染力をなくしたウイルス)」が含まれており、接種によって体内に抗体(こうたい:ウイルスを攻撃する免疫物質)が作られます。抗体がしっかり作られることで感染を防ぎ、重症化を抑える効果が期待できます。特に高齢者や基礎疾患のある方では免疫応答が弱くなりやすいため、ワクチンで免疫を前もって整えることが大切です。
(参考:厚生労働省「インフルエンザワクチンQ&A」)
インフルエンザワクチンはいつ打てばいい?
日本では例年10月ごろから接種が始まり、11月中旬までの接種が推奨されます。これは、抗体ができるまで約2週間かかるためです。厚生労働省やWHO(世界保健機関)も、流行前に抗体を準備しておくことが重要としています。
流行シーズンと接種時期の関係
インフルエンザのピークは毎年12月〜翌年3月頃です。抗体が最も高まるのは接種後2〜4週で、その後3〜4か月で徐々に減少します。そのため、11月上旬に接種しておくと最も効果が高い期間を流行ピークに合わせやすいです。
大人と子どもで接種時期が違う理由
13歳未満の子どもは免疫がまだ十分ではないため、2回接種が必要になる場合があります。一方で成人は1回の接種で抗体ができやすいため、接種時期もやや後ろでも対応可能です。家庭内で感染を防ぐためには、家族全員でタイミングを合わせることが有効です。
予防効果を最大化するためのスケジュール
- 0〜2日後:抗体が少しずつ作られ始める
- 2週間後:予防効果がピークに達する
- 3〜5か月後:効果が持続
流行ピークにあわせるためには、11月中の接種が理想的です。特に受験生・高齢者・基礎疾患のある方は早めの接種が安心です。
インフルエンザワクチンの効果は何時間後から?発現までの目安
接種直後から体は免疫応答を始めますが、抗体が十分にできるのは接種から約2週間後です。そのため、接種当日に「すぐ免疫ができる」わけではありません。研究(Ohmit SE et al., Clin Infect Dis, 2014)によると、抗体価の上昇は10〜14日目でピークを迎えます。
抗体ができるまでの時間
接種後、体はウイルスの一部を「異物」と認識し、抗体を作り始めます。この過程には平均10〜14日かかります。免疫力の弱い方(高齢者・糖尿病患者など)は反応がやや遅れる場合もあります。
接種当日〜数日後の体の変化
接種部位の痛みや赤み、軽い発熱などが起こることがありますが、これは抗体を作る自然な免疫反応です。数日でおさまることが多く、重い副反応はまれです。
発症予防効果が高まる時期
最大の予防効果が出るのは接種2〜4週後。その後3〜5か月間は効果が持続します。
インフルエンザワクチンの効果の持続時間はどれくらい?
免疫効果は平均で約5か月持続します(Hobson D. Lancet, 1972)。したがって、10月〜11月に接種すれば、翌年3月頃まで効果が続きます。
免疫が持続する期間の目安
若年層では4〜5か月、高齢者では3〜4か月が目安です。体質や免疫の強さによって差があります。
なぜ毎年接種が必要なのか?
インフルエンザウイルスは「抗原変異(ドリフト)」を繰り返すため、昨年の免疫が今年の株には効かないことがあります。そのため、毎年新しいワクチンを接種する必要があります。
持続時間が短くなるケースと注意点
免疫抑制剤を使用している方、糖尿病・腎疾患など慢性疾患のある方では、抗体の持続が短くなる傾向があります。早めの接種と体調管理を心がけましょう。
インフルエンザワクチンの対象者と接種回数
インフルエンザワクチンは全年齢で推奨されますが、特に重症化しやすい方には強く勧められています。
子ども・高齢者・基礎疾患のある人の接種のポイント
子どもは免疫の記憶が少ないため2回接種が必要です。高齢者や基礎疾患を持つ方では、肺炎・入院リスクを大幅に下げることが確認されています(CDC, 2023)。
1回接種と2回接種の違い
13歳以上は1回接種、13歳未満の小児は2回接種が基本です。13歳以上は原則1回で十分ですが、免疫が弱い方では2回目を検討する場合もあります。接種間隔は2〜4週間空けるのが一般的です。
(参考:日本小児科学会)
インフルエンザワクチンの副反応と注意点
主な副反応は「腕の痛み・赤み・軽い発熱」などです。まれにアレルギー反応(蕁麻疹・息苦しさ)を起こすことがあります。
よくある副反応と対処法
接種部位の痛み・赤み・軽い発熱などが代表的な副反応です。多くは2〜3日で治まりますが、長引く場合は医療機関へ。
副反応と感染症の違い
発熱があっても1〜2日で下がれば副反応の可能性が高く、長引く場合は感染症の可能性もあります。不安な場合は医療機関にご相談ください。
接種後に気をつけること
接種当日は激しい運動や入浴直後の長湯を避けましょう。
インフルエンザワクチンの費用・助成・予約方法
当院では2025年度のインフルエンザワクチン接種を10月1日から開始しています。
費用の目安と自己負担
費用は、
65歳以上または基礎疾患のある方は1,500円(税込)
一般の方は3,300円(税込)
です。
伊丹市の助成制度について
伊丹市では65歳以上の高齢者に助成があります。詳細は自治体ホームページまたは当院にお問い合わせください。
令和7年度高齢者の定期予防接種(季節性インフルエンザ、新型コロナワクチン)について(接種費用一部公費負担)
接種予約の流れと当日の持ち物
当院では予約制としております。Web・電話予約をご利用下さい。65歳以上の方に関しては伊丹市在住の方はもちろん、伊丹市外(阪神6市1町:尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、三田市、川西市、猪名川町)の方も接種可能のため、マイナ保険証や資格確認証等の住所が確認できるものを持参ください。
よくある質問(Q&A)
ワクチンを打ってもインフルエンザにかかることはある?
あります。予防効果は高いですが100%ではありません。ただし、重症化を防ぐ効果はしっかりとあります。
ワクチンと他の予防接種の間隔はどれくらいあける?
不活化ワクチンであれば間隔を空けずに接種可能です。生ワクチンの場合は4週間空けましょう。
ワクチン接種後に体調不良になったときの対応は?
強い副反応がある場合は医療機関を受診してください。軽い症状は自然に改善することが多いです。
まとめ
インフルエンザワクチンは、接種のタイミング・効果が出るまでの時間・持続期間を理解しておくことがとても重要です。特に40〜60代の方は重症化リスクも上がるため、早めの接種をおすすめします。
つねだクリニックは伊丹市にあり、川西市・宝塚市・尼崎市・池田市からも多くの患者さんにご来院いただいています。糖尿病内科を専門とし、ワクチン接種にも対応。駐車場も完備していますので、安心してお越しください。
(文責:つねだクリニック院長 常田和宏)

