甲状腺腫瘍の症状・原因・検査・治療をわかりやすく解説
- 2025年9月9日
- 甲状腺腫瘍について
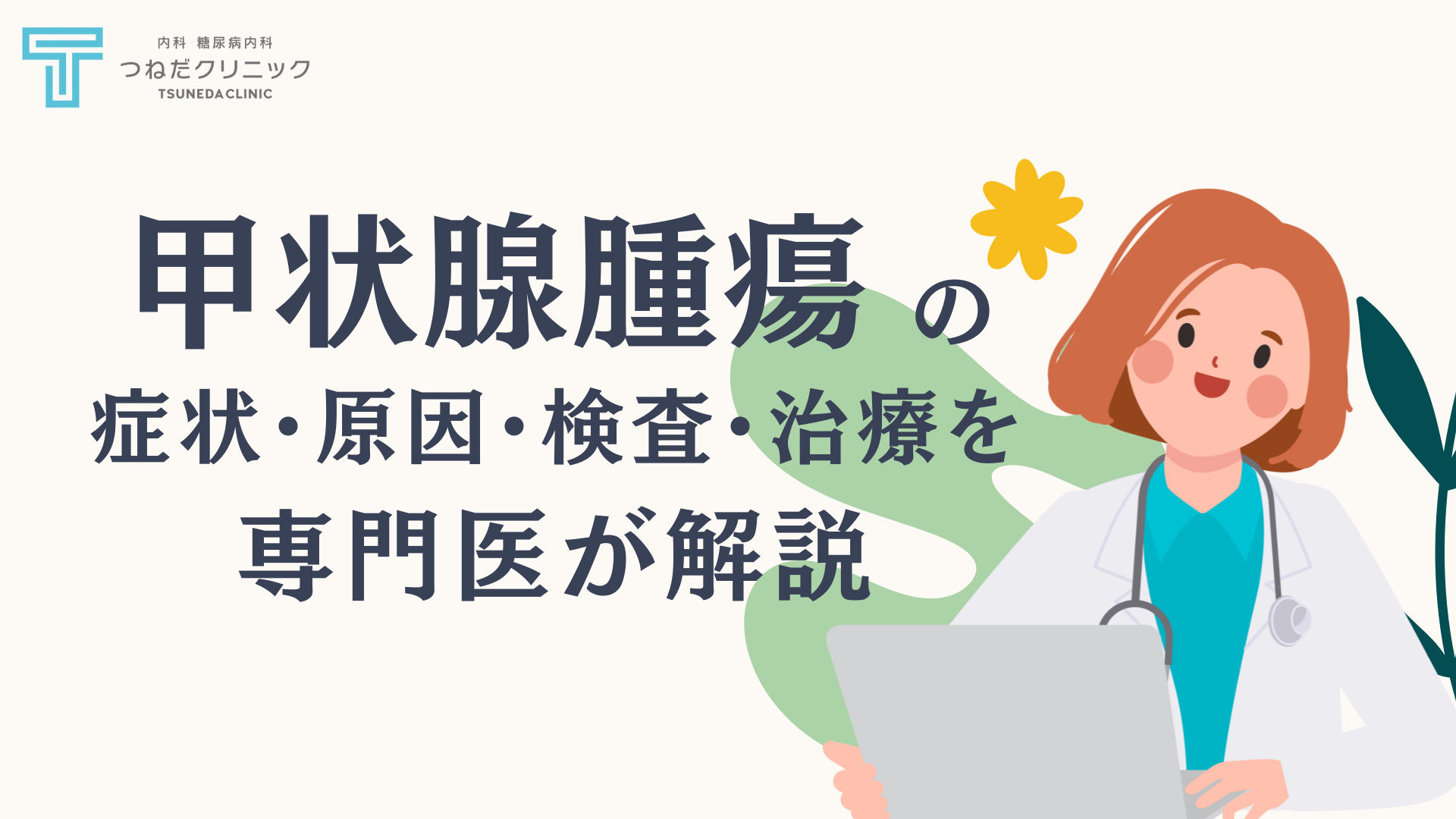
甲状腺腫瘍は、首の前にある甲状腺に「しこり」ができる病気の総称です。健康診断や人間ドックで偶然見つかることも多く、すべてが「がん」というわけではありません。実際には良性の結節が多く、悪性の甲状腺がんは一部にとどまります。ここでは甲状腺腫瘍の特徴と注意点を整理します。
甲状腺腫瘍と甲状腺結節の違い
「甲状腺結節」は甲状腺にできるしこり全般を指し、その中に腫瘍があります。腫瘍には良性と悪性があり、甲状腺がんの可能性がある場合は詳しい検査が必要になります。
良性腫瘍と甲状腺がん(悪性腫瘍)の割合
甲状腺に見つかるしこりの約9割は良性とされます(日本内分泌学会「甲状腺腫瘍診療ガイドライン2018」)。しかし残りの1割程度は甲状腺乳頭がんなどの悪性腫瘍であり、見極めが重要です。
甲状腺腫瘍の主な症状
甲状腺腫瘍は自覚症状が少ないこともありますが、進行すると喉のつっかえ感や、首や声に変化が出ることがあります。
首のしこり・腫れに気づいたら
首の正面に固いしこりを触れる場合、甲状腺腫瘍の可能性があります。痛みがないことも多いため、気づかずに放置してしまうことがあります。
声のかすれや飲み込みにくさ
腫瘍が大きくなると声帯を動かす神経を圧迫し、声がかすれることがあります。また、食べ物を飲み込みにくくなることもあります。
無症状で見つかるケースも多い
多くは健康診断の触診検査で偶然見つかります。症状がなくても早期に受診し、良性か悪性かを確認することが大切です。
甲状腺腫瘍の原因とリスク要因
女性や中高年に多い理由
甲状腺腫瘍は特に女性に多く、更年期以降に発見されやすい傾向があります。女性ホルモンや免疫の影響が関係していると考えられています。
放射線被曝や遺伝との関連
小児期に放射線を浴びた経験や、家族に甲状腺がんを持つ方がいる場合、リスクが高まります。特に甲状腺がんのうち、髄様(ずいよう)がんは遺伝性のこともあります。
橋本病やバセドウ病との関係
自己免疫性甲状腺疾患(橋本病やバセドウ病)に合併して甲状腺腫瘍が見つかることがあります。炎症やホルモン異常が背景に関与していると考えられています。
良性結節の種類
腺腫様(せんしゅよう)甲状腺腫(腺腫様結節)
甲状腺にできる良性のしこりで、最もよく見られるタイプです。1つのしこりとして見つかることもあれば、複数の結節が集まって全体が腫れて見えることもあります。しばしば健康診断の超音波検査で偶然見つかります。大部分は良性で、急激に悪化することはまれです。治療が必要ないことも多いですが、サイズが大きくなったり、圧迫感・違和感が出てきたりした場合には手術が検討されることもあります。
濾胞腺腫(ろほうせんしゅ)
甲状腺ホルモンを作る濾胞(ろほう)細胞が増えてできる良性の腫瘍です。腺腫様結節に比べるとややまれですが、しこりが大きくなって発見されることがあります。特徴的なのは、細胞の形や配置が一見「濾胞がん」と区別がつきにくい点です。そのため、細胞診や手術で組織を詳しく調べて診断されることもあります。ほとんどの場合は良性で、治療後の経過も安定しています。
嚢胞(のうほう)
甲状腺の内部に液体がたまって袋状になった状態を嚢胞(のうほう)と呼びます。中身は血液や分泌液で、大きさによっては首のしこりや違和感として気づかれることがあります。基本的に良性で命にかかわることはありません。症状がなければ経過観察で済むことが多く、しこりが目立ったり不快感がある場合は、針を用いて液体を抜く処置が行われることもあります。
慢性甲状腺炎(橋本病)による結節
自己免疫の異常によって甲状腺に慢性的な炎症が起こる病気が橋本病です。この病気では甲状腺の組織が硬く変化するため、結節のように見える部分が生じることがあります。多くは良性であり心配はいりませんが、画像検査だけでは悪性との区別が難しいこともあるため、定期的な超音波検査や血液検査でのフォローが勧められます。
甲状腺がんの種類
甲状腺乳頭がん
甲状腺がんの中で最も多く、約90%がこのタイプです。女性に多く、10歳代~高齢者まで幅広い年代にみられます。ゆっくり進行することが多く、早期に見つかれば治療で良好な経過をたどるケースがほとんどです。乳頭がんの10年生存率は95%を超えると言われており、がんとしては「極めて予後がいい」です。治療は外科的切除が中心ですが、1cm以下の無症状の微小乳頭がんの場合手術はせずに経過観察する方針をとる場合があります。首のしこりやしつこい声のかすれなどで発見されることがあります。
甲状腺濾胞(ろほう)がん
乳頭がんに次いで多い(約5%)タイプです。甲状腺ホルモンを作る濾胞(ろほう)細胞からできるがんです。血管や甲状腺の外へ広がることがあるため、慎重な診断と治療が必要です。乳頭がんと同様に比較的ゆるやかな進行で予後はよいとされていますが、転移の可能性があるため注意が必要です。
甲状腺髄様(ずいよう)がん
甲状腺がんの約1~2%を占めます。カルシトニンというホルモンを作る傍濾胞(ぼうろほう)細胞からできるがんです。髄様がんではCEAやカルシトニンという検査値が上昇します。遺伝的な要因が関係することがあり、家族性に見つかることもあります。家族性の場合は、同時に副腎、副甲状腺などに病気を伴うこと(多発性内分泌腫瘍症2型)があるため追加での検査が必要です。そのため治療については遺伝子検査と早めの診断を行うことが重要です。
甲状腺未分化がん
1%未満と非常にまれですが、進行が速く、治療が難しいタイプです。急速に大きくなる首のしこりとして見つかることが多いです。早期に専門医の診察を受けることが大切です。
甲状腺腫瘍の検査方法
甲状腺エコー検査(超音波検査)
エコーで腫瘍の大きさや形を確認します。悪性が疑われる場合は形や血流の特徴が参考になります。当院では状況に応じて、医師がその場で甲状腺エコー検査と結果説明を行っております。
穿刺吸引細胞診(FNA)とは
細い針でしこりから細胞を採取し、顕微鏡で良性か悪性かを調べます。甲状腺腫瘍の診断に最も重要な検査です。1cm以上のしこりに対しては一度は細胞診が勧められます。当院では近隣の総合病院耳鼻科医師と病診連携をとって紹介させて頂いております。
血液検査や腫瘍マーカー(カルシトニンなど)
甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4)の測定に加え、髄様癌が疑われる場合はサイログロブリンやCEA、カルシトニンといった腫瘍マーカーも測定します。
CT・MRI・PET検査の役割
進行がんが疑われる場合、頸部や胸部の広がりを評価するためにCTやMRIが行われます。転移検索にはPET検査を用いることもあります。
甲状腺腫瘍の治療法
良性の場合は経過観察が中心
しこりが小さく、良性と診断された場合は定期的な3~6ヶ月ごとのエコーで経過観察を行います。
甲状腺がんの手術療法(部分切除・全摘術)
悪性と診断された場合は手術が基本です。乳頭癌や濾胞癌では腫瘍の広がりに応じて部分切除または全摘術が行われます。
放射性ヨウ素治療や薬物療法
甲状腺全摘後には放射性ヨウ素治療(I-131)を行い、残った甲状腺組織や転移を抑えます。進行がんには分子標的薬が用いられることもあります。
手術後に必要なホルモン補充療法
甲状腺を摘出した場合、レボチロキシン(チラーヂンS)という甲状腺ホルモン薬を毎日内服し、ホルモンを補う必要があります。
甲状腺腫瘍の手術後に注意すべきこと
声のかすれ・声帯麻痺のリスク
手術の際、声帯を動かす反回神経が傷つくと声がかすれることがあります。多くは一時的ですが、回復までリハビリが必要な場合もあります。
カルシウム値の低下と副甲状腺機能低下症
手術で副甲状腺に影響が及ぶとカルシウム値が下がることがあります。しびれやけいれんを感じた場合は早めの対応が必要です。
定期的なフォローアップの大切さ
再発や転移の有無を確認するため、術後も定期的に血液検査やエコーが必要です。
甲状腺腫瘍と生活習慣
ヨウ素を含む食事との関係
海藻類の過剰摂取は甲状腺の働きに影響を与えることがあります。治療中の方は医師の指示に従って調整してください。
日常生活・運動の注意点
手術後やホルモン治療中でも、多くの方は普段通りの生活が可能です。ただし疲れやすい時期は無理を避け、体調に合わせて運動しましょう。
再発予防のために心がけたいこと
バランスの良い食事、十分な睡眠、ストレス管理が全身の免疫を安定させ、再発予防にもつながります。
甲状腺腫瘍と他の疾患との違い
甲状腺腫瘍と甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
バセドウ病は甲状腺ホルモンが増える病気で、甲状腺自体が大きく腫れることがありますが腫瘍とは異なります。ただし両者が併発することもあり注意が必要です。
甲状腺腫瘍と慢性甲状腺炎(橋本病)
橋本病は自己免疫による炎症で、バセドウ病と同様に甲状腺が大きく腫れることはありますがこちらも腫瘍ではありません。ただし慢性炎症の中に結節が見つかることもあります。
伊丹市で甲状腺腫瘍の検査や治療を受けたい方へ
地域の内科・甲状腺専門外来の選び方
甲状腺腫瘍が疑われた場合は、血液検査やエコーを行える医療機関を選ぶことが大切です。
当院で行っている甲状腺腫瘍の診療
当院では問診・血液検査・エコーを行い、必要に応じて細胞診を手配しています。患者さんの不安を和らげるよう丁寧に説明し、最適な医療機関と連携して治療を進めます。
まとめ
甲状腺腫瘍は首のしこりとして見つかることが多く、大部分は良性ですが一部は甲状腺がんの可能性もあります。エコーや細胞診で診断し、必要に応じて手術や放射性ヨウ素治療を行います。術後はホルモン補充や定期的な検査が重要です。伊丹市をはじめ、川西市、宝塚市、尼崎市、池田市からも多くの患者さんが来院されていますので、気になる症状がある方はぜひ気軽にご相談ください。
(文責:つねだクリニック院長 常田和宏)

