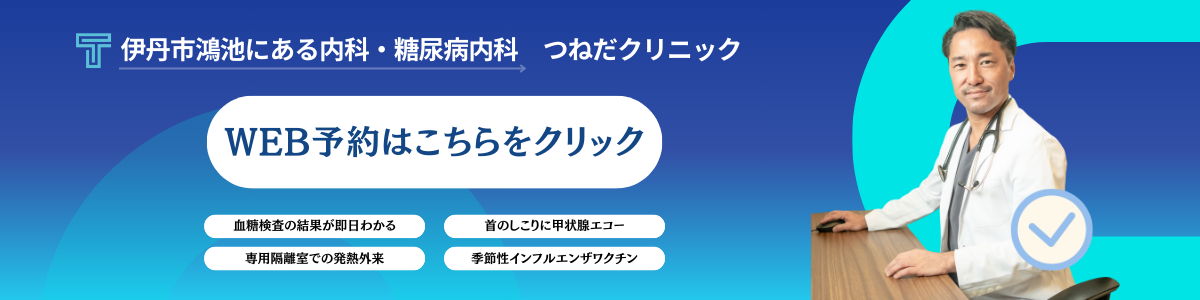帯状疱疹の症状・原因・治療法を解説
- 2025年4月8日
- 帯状疱疹について
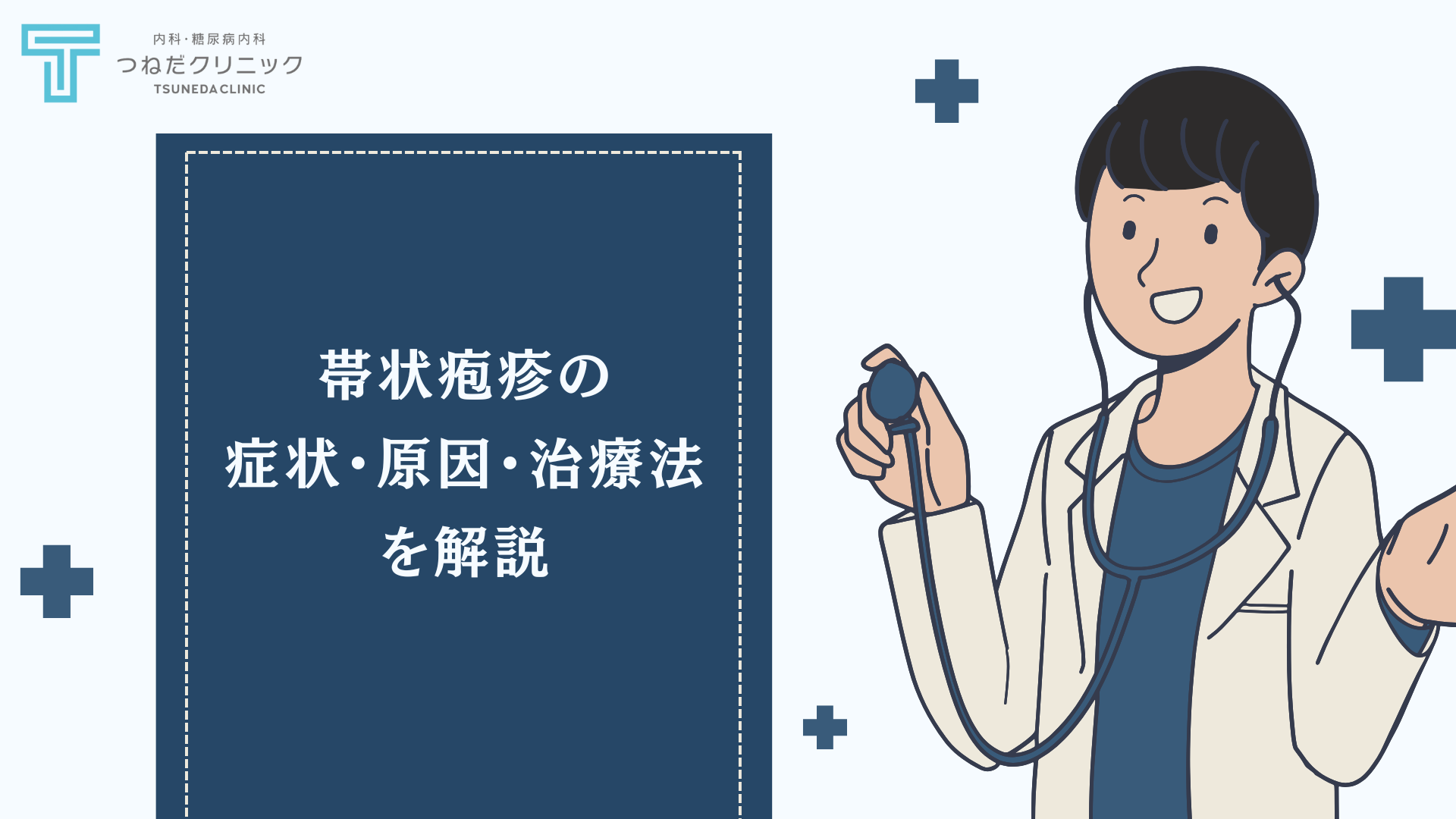
帯状疱疹とは?原因と発症メカニズムを解説
帯状疱疹(たいじょうほうしん)は、「水ぼうそう」と同じウイルス(VZV:水痘・帯状疱疹ウイルス) が原因で起こる感染症です。「え?水ぼうそうって子どもの病気じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はウイルスは水ぼうそう治癒後も体内の神経に潜んでいます。水ぼうそうを経験した後もウイルスは体内に潜伏し、加齢やストレス、免疫力の低下などが引き金となって再活性化し、帯状疱疹として発症します。特に近年は、50代以降の発症率が急増しており、糖尿病や甲状腺疾患を抱える方も要注意です。
帯状疱疹はなぜ起こる?ウイルスの正体と再活性化の理由
帯状疱疹の原因は「水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)」というウイルス。これは水ぼうそうの原因ウイルスでもあります。治った後も、背骨の近くの神経節にひっそりと潜伏し、私たちが油断したスキに再活動!この“再活性化”のきっかけとなるのが、加齢・ストレス・過労・感染症などで低下した免疫力です。「疲れてるときに限って風邪をひく」ようなもの。現代人の敵「ストレス社会」と帯状疱疹には深い関係があります。糖尿病や免疫抑制剤を使っている方もリスクが高いため、予防と早期発見がカギです。
帯状疱疹が発症しやすい年代とリスク因子
帯状疱疹は、50歳以上の2人に1人が発症すると言われており、年齢とともにリスクが高まります。その他にも、以下のようなリスク因子があります:
- 糖尿病・がん・慢性疾患のある方
- ストレスや疲労が蓄積している方
- 免疫抑制治療を受けている方
- 女性の方がやや多い傾向あり
驚くかもしれませんが、帯状疱疹ワクチンは50歳以上の方に推奨されています。とくに内科クリニックを定期的に受診している方は、主治医に予防接種の相談をしておくと安心です。
帯状疱疹の主な症状と見分け方
帯状疱疹の典型的な症状は「片側の皮膚にできる水ぶくれと痛み」です。特徴的なのは、左右どちらか一方だけに症状が出ることです。これは、ウイルスが神経に沿って再活性化するためです。
最初は「皮膚がピリピリするな」と感じ、次第に赤い発疹→水ぶくれ→かさぶたへ変化していきます。発疹が現れる前の「前駆症状」も見逃さないでください。痛みだけが先に出ることもあり、「筋違い」や「ぎっくり腰」と間違えることもあります。「痛み+発疹=帯状疱疹」のサインです!
初期症状と特徴的な痛み・発疹について
初期には、皮膚がピリピリ・チクチクする違和感から始まります。その1~3日後に帯状に赤い発疹が出現し、水ぶくれが形成されるのが特徴です。この発疹は神経に沿っており、体の片側だけに出ます。
痛みの質は「焼けるような痛み」「針で刺されたような痛み」など、人によって異なりますが、かなり強い痛みを伴うことが多いです。見た目より痛みが強い場合、「おかしいな」と思ったら、早めに内科か皮膚科へ。発症から72時間以内に治療を始めることが重要です。
神経痛・しびれが残る帯状疱疹後神経痛とは?
帯状疱疹の厄介な合併症が「帯状疱疹後神経痛(PHN)」です。発疹が治った後も、数ヶ月〜数年にわたり神経の痛みが残ることがあります。特に60歳以上の方や、治療開始が遅れた方に多く見られます。
ピリピリとした痛みや、しびれ、灼熱感などが慢性的に続き、日常生活の質(QOL)を著しく下げる原因に。だからこそ、早期治療+予防が重要になります。ワクチン接種や初期治療のタイミングが未来の自分を守ります。
帯状疱疹の治療法と受診のタイミング
帯状疱疹は早期治療が非常に重要です。発症後すぐに治療を始めることで、症状の悪化や後遺症を防ぐことができます。「もしかして帯状疱疹かも?」と感じたら、できるだけ早く受診しましょう。
抗ウイルス薬・鎮痛薬などの治療内容
帯状疱疹の治療は、抗ウイルス薬+痛みの管理がセットです。代表的な抗ウイルス薬には以下のものがあります:
- バラシクロビル(バルトレックス)
- ファムシクロビル(ファムビル)
- アシクロビル(ゾビラックス)
発症から72時間以内に服用を開始することで、神経へのダメージを最小限に抑えることが期待されます。加えて、痛みに対してはロキソプロフェンなどのNSAIDsや、神経痛用のプレガバリン(リリカ)が使われることもあります。
帯状疱疹は何科にかかればいい?皮膚科・内科の違い
「帯状疱疹って何科で診てもらうの?」と悩む方が多いですが、皮膚の発疹+痛み=皮膚科 or 内科のどちらでもOKです。
糖尿病などの基礎疾患がある場合は、内科で一貫して管理するメリットもあります。
発疹が明らかでなければ、「念のため皮膚科へ」ということもありますが、まずは身近な内科で相談するのがベストです!
帯状疱疹を発症したときの注意点と日常生活の対応
帯状疱疹を発症したら、安静とストレス回避が第一。無理に仕事や運動を続けると、症状の悪化や神経痛の残存リスクが高まります。
また、患部は清潔に保ち、無理にかかないように注意しましょう。シャワー中心がおすすめです。
感染予防と家族への配慮(帯状疱疹はうつるのか?)
帯状疱疹は他人に直接うつることはありませんが、注意すべき点もあります。
・水ぼうそうにかかったことがない人に、水痘として感染する可能性あり
・特に妊婦さん・乳児・免疫が弱い方には接触を避ける
発疹部位はできるだけガーゼで覆うことが大切です。ウイルスは水ぶくれの中に存在するため、破れた場合の飛散には注意しましょう。
家庭内でもタオルの共用を避け、手洗い・消毒を徹底すると安心です。
安静・ストレス管理・食事など生活面のポイント
帯状疱疹の治療中は、「体を休めること」が最大の治療薬です。
- 睡眠をしっかりとる
- バランスの良い食事(ビタミンB群・たんぱく質)
- アルコールや刺激物を控える
- ストレスを溜めすぎない(軽いストレッチや趣味の時間も◎)
また、再発や重症化を防ぐために、帯状疱疹ワクチンの接種も検討してみてください。ワクチンは内科での接種が可能ですので、お気軽にご相談ください。
まとめ
帯状疱疹は、早期の受診と適切な治療で回復が早まり、後遺症を防ぐことができます。 特に50代以上の方や免疫力が下がりやすい方は、日頃から体調管理やストレス対策を心がけることが大切です。
伊丹市・川西市・宝塚市にお住まいの方で、帯状疱疹かな?と思ったときには、ぜひ早めに当院へご相談ください。
(文責:つねだクリニック院長 常田和宏)