糖尿病合併症⑧糖尿病と認知症の関係とは?
- 2025年7月22日
- 認知症について
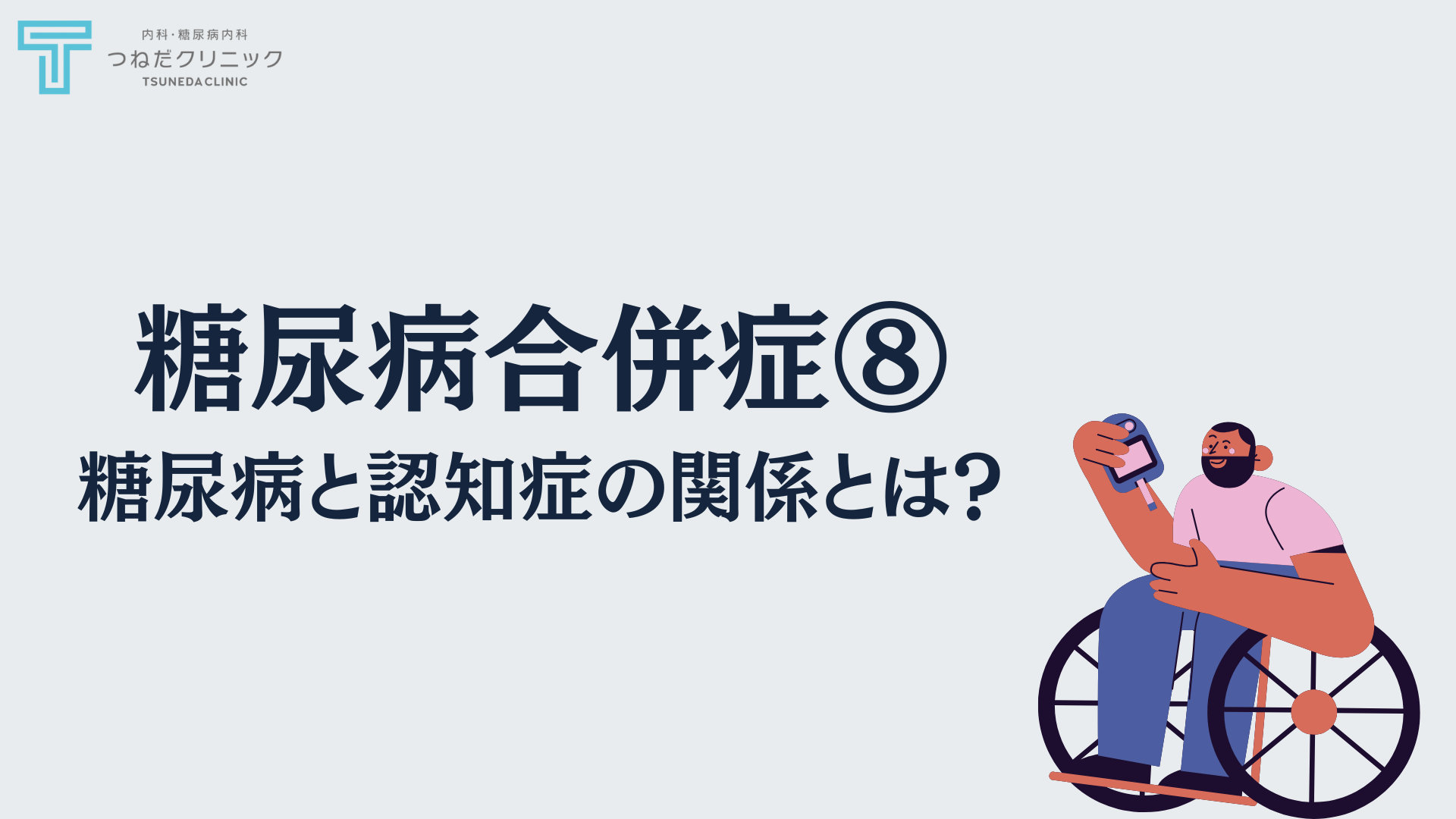
糖尿病は血糖値が慢性的に高くなることでさまざまな合併症を引き起こす病気ですが、近年注目されているのが「認知症」との関係です。これまでの研究から、糖尿病患者では認知症の発症リスクが1.5〜2倍に高まることが示されています(Luchsinger, 2010; Prince et al., 2014; Profenno et al., 2010)。本記事では、糖尿病と認知症の関係、原因と予防、そして日常生活でできる対策までを詳しくご紹介します。
糖尿病と認知症の関連性
血糖コントロールの乱れが脳に与える影響
血糖値が乱高下することで、脳は酸化ストレスや慢性炎症にさらされ、神経細胞の損傷が進行します。また、低血糖発作は一過性の記憶障害や意識障害を引き起こすだけでなく、繰り返すことで認知機能の低下に直結します。さらに、HbA1cが8%以上の患者は、認知症の発症率が高いことが知られており、安定した血糖管理が脳を守る鍵となります。(Yaffe K et al., Arch Intern Med. 2011)
アルツハイマー型認知症との関係
糖尿病によりインスリン抵抗性が高まると、脳内でのアミロイドβの排出が妨げられることがわかってきています。このアミロイドβはアルツハイマー型認知症の主な原因物質とされており、糖尿病とアルツハイマー病の発症リスクは密接に関係しています。GLP-1受容体作動薬(例:リラグルチド)は、このインスリン抵抗性を改善し、神経保護効果が期待されています(Holscher C. Front Neurosci. 2014)
糖尿病による認知症リスクを高める要因
動脈硬化と脳血管障害
糖尿病は動脈硬化の進行を加速させ、脳の血流障害を引き起こします。これにより「血管性認知症」のリスクが増加します。頸動脈のプラーク形成や、微小血管の閉塞は、認知機能低下の重要な原因の一つです。
慢性的な炎症と酸化ストレス
糖尿病は全身的な慢性炎症状態を引き起こし、これが神経細胞の変性を促進します。また、酸化ストレスの増加も脳機能に悪影響を与えるとされており、これらの影響が重なることで認知症リスクが高まると考えられています。
糖尿病患者が認知症を予防するには?
血糖値の安定管理が最優先
認知症予防の基本は、血糖値を急激に上下させない「安定管理」にあります。HbA1c値は7.0%未満を目標に、低血糖を避ける治療戦略が推奨されます。SGLT2阻害薬(例:エンパグリフロジン)は、心血管・腎保護効果に加えて低血糖リスクが低いため、高齢糖尿病患者にも適しています(Zinman B et al., NEJM. 2015)。
食事・運動・睡眠の3本柱
- 食事:バランスのとれた低GI食品中心の食事を心がけましょう。
- 運動:有酸素運動(ウォーキングなど)を週150分程度。
- 睡眠:7〜8時間の質の良い睡眠が脳の回復に役立ちます。
これらを継続することで、血糖だけでなく認知機能の維持にもつながります。特にウォーキングなどの中等度運動は、脳の血流を改善し、記憶力の維持に有効です。糖尿病治療と認知症予防は、生活改善の延長線上にあります。
糖尿病と認知症の治療薬について
認知症に用いられる薬剤の例
アルツハイマー型認知症の治療薬として、日本で承認されている代表的な薬剤には以下があります:
- ドネペジル(商品名:アリセプト)
- ガランタミン(商品名:レミニール)
- メマンチン(商品名:メマリー)
- リバスチグミン(商品名:イクセロンパッチ)
これらは認知機能の維持・改善を目的とした薬であり、早期に使用を開始することで進行を遅らせる可能性があります。
糖尿病薬の選択も重要
高齢の糖尿病患者では、認知機能に配慮した薬剤選択が求められます。たとえば、低血糖のリスクが高いSU薬(例:グリメピリド)は慎重に使うべきです。一方、DPP-4阻害薬(シタグリプチン)、GLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬などは、認知機能に悪影響を及ぼしにくいとされ、安全性の高い選択肢といえます。
医科・介護・家族の連携がカギ
多職種連携で早期対応を
糖尿病と認知症は、それぞれが他の健康問題と複雑に絡み合うことがあります。内科、神経内科、歯科、ケアマネジャー、家族が連携することで、早期発見・早期対応につながります。
家族の理解と支援が不可欠
認知症の早期兆候を見逃さないためにも、家族の観察と支援がとても大切です。糖尿病治療の継続にも家族の関与は欠かせません。また、認知機能に不安を感じたときに、本人が受診しやすいようサポートすることも大切です。家族が正しい知識を持つことが、患者さんのQOL(生活の質)向上につながります。
まとめ
糖尿病は認知症のリスクを高める重大な要因の一つです。しかし、日常の血糖管理と生活習慣の見直し、そして医療機関・家族との連携により、リスクを軽減することが可能です。当院では伊丹市、川西市、宝塚市、池田市、尼崎市から多くの患者さんが来院され、認知症予防を含めた包括的な糖尿病管理を行っています。気になる症状があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
(文責:つねだクリニック院長 常田和宏)

